皆さま、こんにちは、大和市鶴間にあるスギヤマ歯科医院、院長の杉山順一です。
私たちは日常、花粉症や食べ物をはじめとしてさまざまなアレルギー物質に囲まれて生活しています。
そんな中で今回は歯科診療でアレルギー反応を起こす可能性のあるものについて書いてみます。
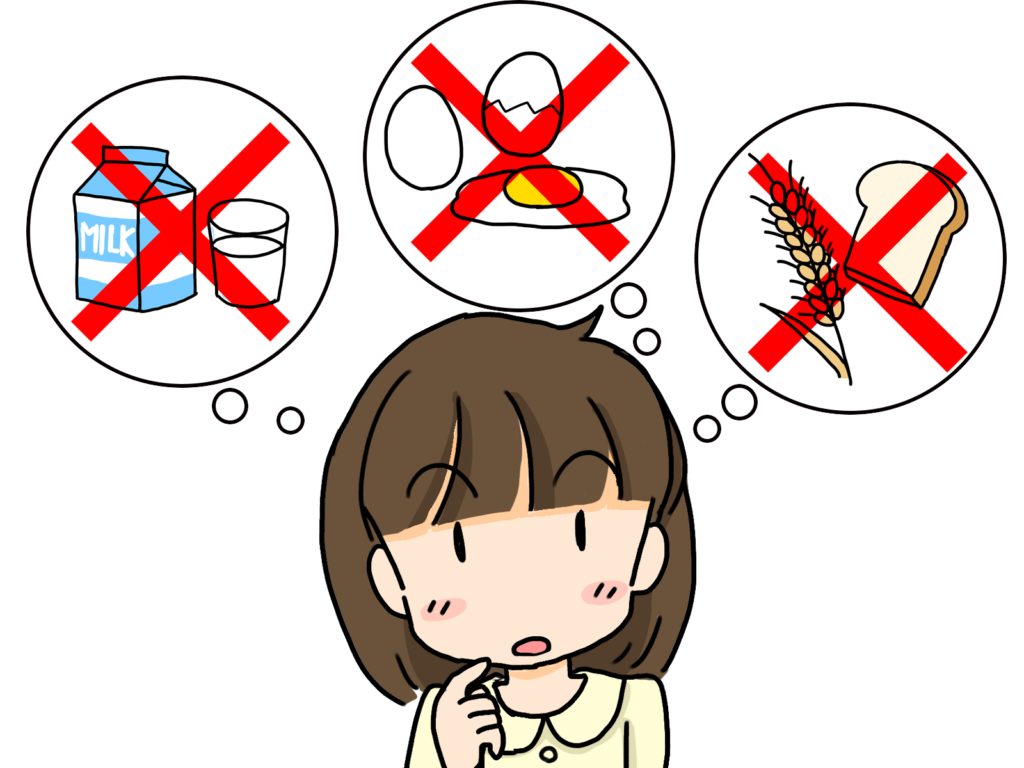
1、局所麻酔薬
局所麻酔薬は歯科診療では最も使用頻度の高いもので、患者さんへのアンケートでは局所麻酔時の異常を経験したことがあると答えた人が26%もあったとのことです。
ただ、そのほとんどは血管迷走神経反射で、局所麻酔薬での真のアレルギー発現は1%以下に過ぎないと言われています。
2、樹脂材料(レジン)
レジンは歯科診療になくてはならないものです。アレルギー性接触皮膚炎や喘息発作を起こしますが、頻度は1%程度と言われています。
3、歯科用金属
歯科治療材料の金属によるアレルギー症状は有名です。特にニッケルは最も一般的なアレルギー原因物質で、腕や足の裏の皮膚炎のみならず口腔灼熱感、舌のしびれ感などの症状が出ます。
他にもクロムやコバルトもアレルギーが出やすい金属です。
4、ラテックス
歯科診療では口腔粘膜に術者のラテックスが常に接触するので、患者さんに刺激性接触皮膚炎やアレルギー性接触皮膚炎が起こります。バナナ、アボガド、キウイなどのアレルギーがあるとラテックスアレルギーを起こしやすいです。
その他にも歯科診療でよく使用される、ホルムアルデヒド、酸化亜鉛ユージノール、次亜塩素酸ナトリウムなどによるアレルギーもあります。
5、内服薬
抗菌薬と鎮痛薬でのアレルギーもあります。
抗菌薬は歯科診療でよく処方されます。アレルギー反応を起こしやすい抗菌薬としてペニシリン系やセフェム系の抗菌薬があげられます。(ペニシリンアレルギー)
NSAIDs(エヌセイズ、非ステロイド抗炎症薬)と呼ばれる解熱消炎鎮痛薬も歯科ではよく処方されます。アレルギー症状としては、アスピリン喘息発作や鼻炎の症状が出る気道型とじんましんや浮腫などの皮膚症状が出る皮膚型があげられます。
アレルギーの反応は即時型と遅延型があり、即時型はアナフィラキシーと言われ、じんましん、気管支けいれん、低血圧などの症状が数分で出ます。遅延型は接触皮膚炎としてかゆみ、紅斑、丘疹、水疱が2〜3日後に出ます。
まとめ
アレルギーは歯科診療のみならず日常生活で常に気を付けておく必要があります。
歯科診療で過去になにがしかの症状を経験した場合や、内服薬で症状が出たことがある場合は、自分でメモしておき、アレルギーかどうかはっきりしていなくても診療の際に一言申し出ていただけると幸いです。


