皆さま、こんにちは、大和市鶴間にあるスギヤマ歯科医院、院長の杉山順一です。
近年、学齢期の児童に口唇閉鎖不全(普通にしている時にくちびるを閉じずに口が開いたままになる)の増加が目立つようになり、児童のお口の機能に問題が生じていることが指摘されてきています。
いつも口が開いていて(口ぽかん状態)その結果、口呼吸が疑われる児童がかなりの割合で見られることが統計的にわかってきています。
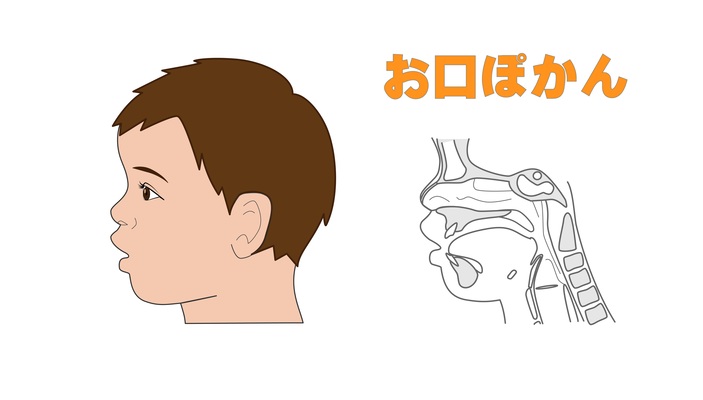 学齢期の前、乳幼児期にさかのぼってみると、乳歯が生えてきても頻繁な指しゃぶり癖やおしゃぶりの常用癖があると、上下の口唇が接する機会が減少し、さらにしゃぶっている間は舌を前に突き出す癖が続くことで口唇閉鎖の習慣がつきにくくなり、さらに年齢を経てもこれらの行為が続くと前歯の突出や開きによって前歯に空隙ができて嚥下が難しくなり、その空隙を舌で塞いで嚥下しようとして更なる舌癖や異常嚥下癖が起こってくるような悪循環を起こします。
学齢期の前、乳幼児期にさかのぼってみると、乳歯が生えてきても頻繁な指しゃぶり癖やおしゃぶりの常用癖があると、上下の口唇が接する機会が減少し、さらにしゃぶっている間は舌を前に突き出す癖が続くことで口唇閉鎖の習慣がつきにくくなり、さらに年齢を経てもこれらの行為が続くと前歯の突出や開きによって前歯に空隙ができて嚥下が難しくなり、その空隙を舌で塞いで嚥下しようとして更なる舌癖や異常嚥下癖が起こってくるような悪循環を起こします。
また、学童期に発症しやすいと言われている扁桃腺の肥大やアレルギー性鼻炎などの病気があると鼻で呼吸することがが困難となり、ますます口で呼吸することが多くなります。口呼吸が常態化すると口唇閉鎖不全と低位舌、口腔周囲筋の筋力低下などを起こしやすくなります。

また、顎が小さくなってきたために歯並び異常や不正咬合(特に前歯の前突や開き)が起こることによって口唇閉鎖が困難になると、嚥下時に口の前を閉鎖しようとして舌の突出が起こりやすくなります。
乳歯から永久歯への交換期(おおむね小学校の時期)には、正常でも一時的に歯並びに空隙が生じたりします。それを気にすると咀嚼や発音に影響が出てきて、その時に口唇閉鎖力の弱い児童は舌を突出させることでその空隙を塞ごうとする癖も生じやすくなります。
学齢期になっても吸指癖や吸唇癖、舌突出癖などの見られる小児児童には本人の自覚を促して習癖を中止してゆく指導が必要になります。生活習慣や家族環境、食習慣を含めておりを見て癖をやめてゆく周りの人の支援が大切になります。
口唇を閉じて奥歯でよく噛んでから嚥下するという食べ方を習慣化してゆくことが大切です。


